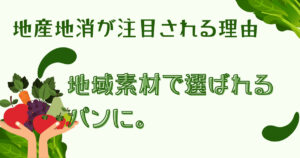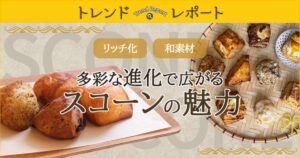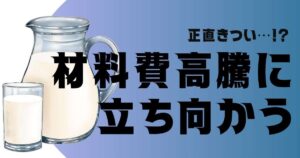地域素材で選ばれるパンに。いま、地産地消が注目される理由
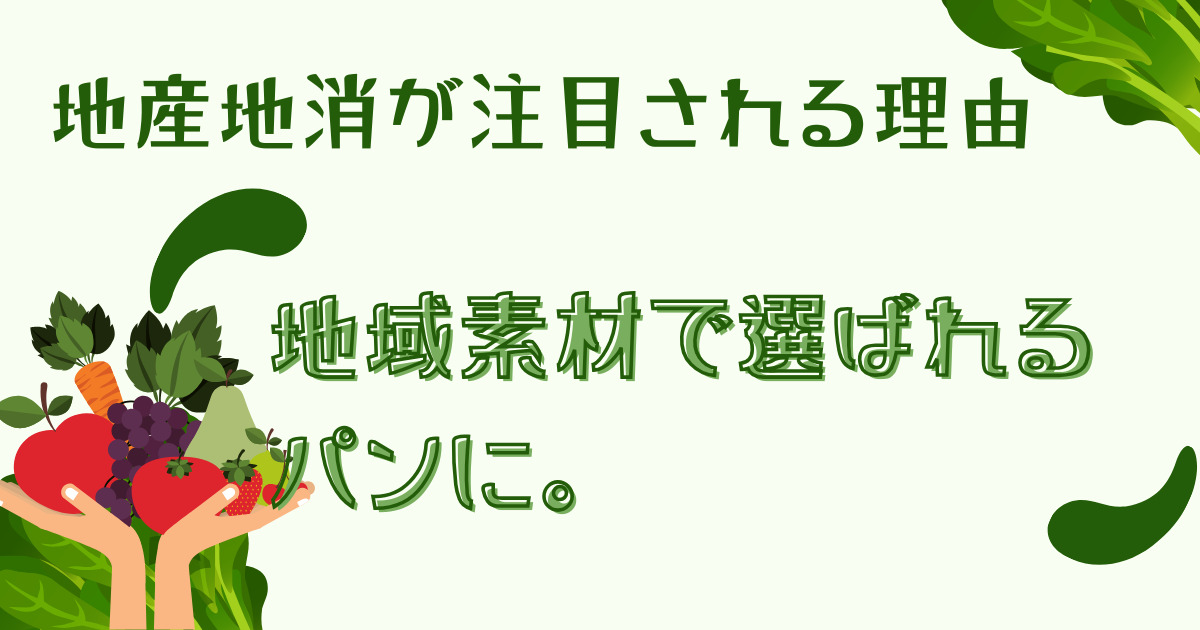

「もっとおいしいパンを」「もっと選ばれるパンを」――
その答えが“地元”にあるかもしれません。
国産小麦や地域の食材を使うパン作りが、いまパン業界の中で静かに広がっています。
環境への配慮、地域とのつながり、そして他店にはない“背景”を持つ商品。
地産地消は、いまや“良いこと”ではなく、“強み”になり得る選択肢です。
なぜ今、国産小麦や地域食材が注目されているのか?

農林水産省の統計によれば、パン用として国産小麦が使用される量は、ここ数年で着実に伸びています。背景には以下のような複数の要因があります。
🍞消費者の安心志向と地元意識の高まり
食品の“産地”に注目する人が増え、「地元のもの」「顔の見える素材」を評価する傾向が強くなっています。
🍞環境負荷を減らす取り組みへの共感
長距離輸送を前提とする原材料に比べ、地元で採れた素材はCO₂排出量の少ない“エコ”な選択肢として受け入れられています。
🍞仕入れの多様化・安定化への工夫
世界的な物流混乱や円安の影響で、輸入小麦への依存リスクを下げる意味でも、国産原料に目を向ける動きが出ています。
🔹参考:農林水産省「国内産麦の生産と流通の動向(PDF)」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/mugi_zyukyuu/attach/pdf/index-10.pdf
地域素材で“売れるパン”を生む工夫とは?

地産地消はただの「取り組み」ではなく、商品価値に直結する“戦略”です。以下のような活用が広がっています。
🍞季節の農産物を使った“今しか買えないパン”
例)旬の柑橘やりんごを使ったスイーツパン、地元野菜を練り込んだ惣菜パンなど
🍞地元加工品との組み合わせ
例)地元の味噌やジャム、酒粕、茶葉などを使い、地元産×地元製品のダブル訴求
🍞パンミックスや粉で地域PR
地元産小麦の品種や栽培方法にこだわったブレンド粉の使用をPOPやパッケージで紹介
こうした「地域性」を前面に出したパンは、SNSや観光客向け、ギフト商品としても選ばれやすくなります。
🔹参考:農文協「パンとラーメンの地産地消から考える食料安保」
https://www.ruralnet.or.jp/syutyo/2022/202211.htm
パン屋が“無理なく”始めるために考えたいこと

すべてのパンを地産地消対応に切り替える必要はありません。
以下のような「小さく始める工夫」が、継続と差別化のカギになります。
「1品だけ地域食材パンをつくる」
「仕入れ先を農家や地元業者と直接つなぐ」
「“限定商品”として仕掛ける」
また、店舗内の掲示やSNSで「この素材はどこで育ったか」「誰がつくったか」を伝えるだけでも、共感を得るきっかけになります。
パンの味に加え、「背景」も買ってもらう時代だからこそ、有効な手法です。

“地元の素材で焼くパン”という考え方は、決して珍しいものではなくなりました。
それは、環境配慮というより、「ちゃんと選ばれる理由をつくる」ための実務的な戦略でもあります。
パンの味・香り・食感だけでなく、その向こうにある「地域性」や「人の顔」が伝わるパンは、記憶に残るパンになる。
いま、“足元”にこそ、次のヒントが眠っています。