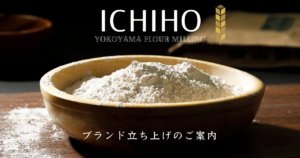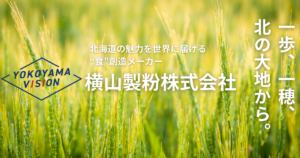5分でわかるパネトーネ ~歴史・起源・雑学~

パネトーネの歴史と魅力を探る

年末が近づくと、ヨーロッパのベーカリーでよく見かける「パネトーネ」。
イタリア・ミラノ発祥のこの発酵菓子パンは、一般的なパンとは大きく異なる製法で作られ、数週間〜数ヶ月の常温保存が可能という特性をもっています。
日本のベーカリーでも少しずつ製造事例が増えており、業界の技術的関心も高まりつつある「パネトーネ」について、その発祥、特徴、製造技術をわかりやすく解説します。
パネトーネの歴史とイタリアでの位置づけ

パネトーネは、イタリアのミラノで19世紀に商品化された発酵菓子パンです。中世から類似の菓子は存在していたものの、現在のような高加水・多脂肪・高糖質の生地と、ドライフルーツをふんだんに使った形態が定着したのは、19世紀後半〜20世紀初頭とされています。
特に1930年代、イタリアの大手製パンメーカー「モッタ(Motta)」と「アレグリーニ(Alemagna)」が工業生産を確立したことで、ミラノ発の伝統的なパネトーネはクリスマスの定番商品として全国に広まりました。
イタリアでは現在でも、12月に入ると各家庭や職場で「パネトーネを誰が持ってくるか」が話題になるほど一般的な風物詩で、スーパーマーケットからパティスリーまでさまざまな価格帯の商品が出回ります。
パネトーネの製法と特徴

パネトーネがユニークなのは、酵母の扱いにあります。一般的なイーストではなく、「リエビト・マードレ(Lievito Madre)」と呼ばれる自然酵母(固形の発酵種)を用い、少なくとも36〜72時間という長い発酵工程を経て製造されます。
この天然酵母は、乳酸菌と酵母が共存することでpHが下がり、保存性と風味のバランスを両立させます。バター、卵黄、砂糖といった水分活性を下げる素材を高配合することで、水分が多くてもカビが生えにくく、結果として数週間〜2ヶ月の常温保存が可能になります(保存環境による)。
この「発酵により保存性を高める」という思想は、日本の麹文化とも通じるものであり、冷蔵流通に頼らずに保存期間を確保できるという点で注目されています。
食感と見た目を保つユニーク手法

パネトーネの見た目の特徴といえば、高さのある丸いドーム型。
これは型に生地を流し入れて焼成することで形成されます。しかし、焼き上げた直後には内部が非常に柔らかく、重力によって萎んでしまう可能性があります。
そこで本場イタリアの職人は、焼成後すぐに鉄串などで底を貫通させ、上下逆さまに吊るして冷ますという手法を用います。これにより内部の構造が崩れるのを防ぎ、ふわっとした食感を保ったまま仕上げることができます。
この工程は一見ユニークですが、品質保持のために極めて合理的。高温多湿の日本では特に注意すべきポイントです。
サクッとまとめ!
日本ではまだ限られたベーカリーでしか見かけないパネトーネ。
長期保存可能なパン菓子としてのポテンシャルは大きく、冬の売上確保やギフト需要にも対応できる商品です。
製造に手間はかかりますが、発酵の知見やレシピ開発に取り組む価値は十分。
天然酵母を活かした発酵菓子という視点から、ぜひ一度、自店なりのパネトーネづくりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。