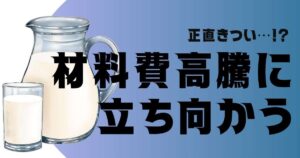5分でわかるアレパ ~歴史・起源・雑学~

アレパの歴史と魅力を探る

とうもろこし粉と水をこねて焼くだけなシンプルなパンですが、驚くほどバリエーション豊かで日常に根づいた存在。ベネズエラやコロンビアの家庭では日々食べられているこの主食パンには、パンづくりの原点を感じさせる知恵と工夫が詰まっています。
本記事ではそんな「アレパ」の魅力とともに、起源や歴史などの雑学を紹介します!
アレパの起源と歴史

「アレパ」はベネズエラやコロンビアを中心に日常食として長く愛されているパンの一種。とうもろこし文化が根づくラテンアメリカでは、小麦よりも前に「マサ(masa)」と呼ばれるとうもろこしの生地が主食でした。
現在では「プレクックド・コーンフラワー(調理済みとうもろこし粉)」が普及し、家庭でも数分で作れる手軽さが人気をですが、伝統的には乾燥とうもろこしをすりつぶし、ぬるま湯で練ってから、鉄板や粘土の窯で焼き上げていました。チーズや煮込みを挟んだりと、具材を選ばず食べられるため「ごはん」のような存在でまさに“南米版の白米”といえます。
アレパの製法と特徴

アレパの基本材料は、とうもろこし粉、水、塩だけ。にもかかわらず、焼き方や水分量の微調整、粉のブランドの違いで、まったく異なる食感が生まれます。
表面はカリッと、中はもっちり。
厚く成形してふっくら焼いた「アサード(鉄板焼き)」タイプや、揚げた「アレパ・フリタ」、薄く焼いてサンドにした「アレパ・レイナ・ペピアダ」など、用途に応じて形状が違います。
加水率の違いで、ぱっくりと割れやすいものと、もっちり閉じるものができるという点も、加水率に敏感なパン職人には興味深いはず。
シンプルだからこそ!アレパの汎用性

アレパの自由さは、家庭によって焼き方もサイズも味付けもバラバラなところに現れています。
ベネズエラでは「アレペーラ」と呼ばれるアレパ専用のホットプレートもあり、各家庭に必ず1台あるとも言われるほど。日本で言えば「ホットケーキ用フライパン」や「たこ焼き器」のような存在です。
おにぎりのように中に具材を練り込む家庭もあり、なんと“スイーツ系アレパ”も存在。ココア粉やバナナを混ぜたり、ジャムを添えて食べることもあるそうです。
サクッとまとめ!
アレパは「とうもろこし粉と水だけ」の極めてシンプルな配合にも関わらず、食文化や家庭の工夫を映す鏡のような存在です。グルテンフリー、簡易調理、具材との相性のよさ、焼成方法の自由さなどどれも今のベーカリートレンドに通じる要素が詰まっています。
この記事を通じて、パン業界の皆様にアレパの魅力を再発見し、新たなインスピレーションを得ていただければ幸いです!