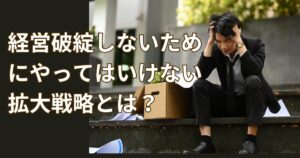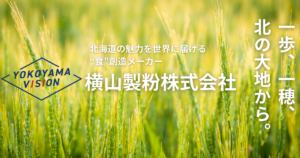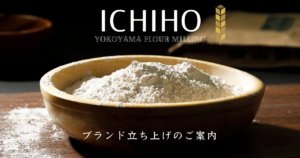経営破綻しないためにやってはいけない拡大戦略とは?
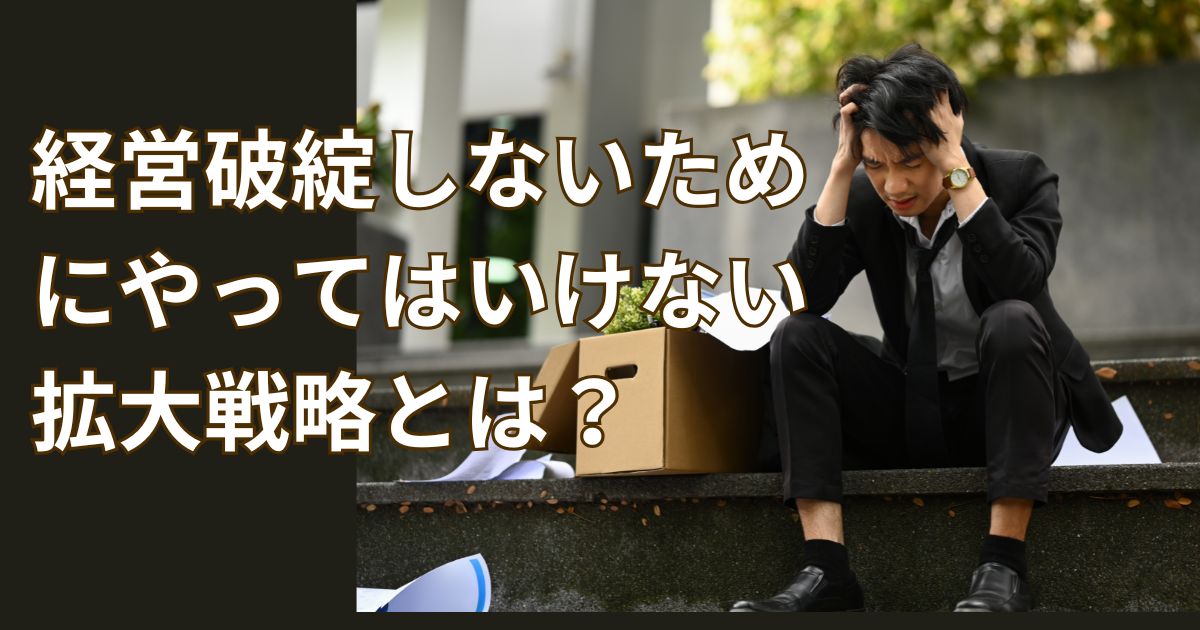
経営破綻しないためにやってはいけない拡大戦略とは?
「2店舗目を出したのに赤字続き…」「機械を買い替えたら資金が回らなくなった」
パン屋経営では、売上が伸びていても潰れるケースが少なくありません。
本記事では、経営の現場で陥りがちな“拡大の落とし穴”を具体例と共に解説し、失敗しないための判断軸を提供します。
「売上=利益」ではない!拡大が危険になる3つのパターン

よくある“経営破綻パターン”は以下の通りです:
- 売上は増えたが、固定費がそれ以上に増加
→ 店舗拡大後の家賃・人件費・機械ローンが利益を食い尽くす。 - 客数の分散で既存店の売上が落ちる
→ 2号店開業で常連が分かれ、両店舗とも中途半端に。 - 管理の手が回らず、品質・サービスが低下
→ シェフが現場から離れ、ブランド力も失速。
つまり、拡大=成功とは限らないということ。
勢いで進める前に「本当に今がそのタイミングなのか?」を立ち止まって考える必要があります。
拡大判断の前に確認したい5つのチェックポイント

次のチェックリストは、“まだ拡大すべきではない”兆候を見逃さないためのものです。
□ 既存店舗の利益を安定して確保できているか?
□ シェフが1日の大半を「現場」ではなく「管理」に回す余裕があるか?
□ 新店舗の資金は「借入」だけでなく、自己資金が含まれているか?
□ 人材育成が間に合っているか?店舗を任せられる人はいるか?
□ 失敗した場合の「撤退ライン」と「撤退資金」が計算されているか?
1つでも「No」があるなら、拡大より“足元の安定”を優先する段階です。
やってはいけない!“なんとなく”拡大の典型例

よく見かける危険なケースをご紹介します。
• 「常連さんに“2号店まだ?”と言われてその気に…」
•「空き物件が出たからとりあえず契約…」
•「補助金があるうちに拡張しないと損…」
これらは経営の“理由”ではなく“きっかけ”に過ぎません。
事業の目的や経営戦略と結びついていない拡大は、数年後にしわ寄せが来るリスクが高いです。
“小さく強く”がいまの時代に合っている理由

最近、大きく展開するよりも「地元密着型・高収益モデル」に注目が集まっています。
• 1店舗でも十分な年商と利益率がある強い個店の存在
• EC・モバイルオーダー・卸など、多店舗化しなくても売上を増やす方法が拡大
• 人手不足・物価高など“外部リスク”が多い時代、規模より“柔軟性”が経営のカギ
“広げる”より“深める”経営。これがこれからの成功モデルと言えるかもしれません。
まとめ
店舗を増やす、機械を買う、スタッフを雇う…。
どれも「攻めの経営」のように見えて、準備不足なら“落とし穴”になりかねません。
拡大することがゴールではなく、長く続けられるパン屋・菓子屋であることが最大の価値です。
「今、やるべきか?」と自問することから、次の一歩を踏み出しましょう。
こちらの記事もおすすめ


この記事を書いたライター

株式会社グロ―アップ編集部
加納 麻衣
インタビュー相手の魅力を発見するのが得意。
「どんな人にも物語がある!」をモットーに丁寧に伝えていきます。
小説を書くことが趣味