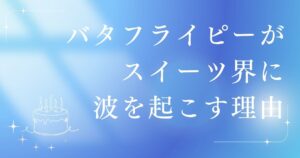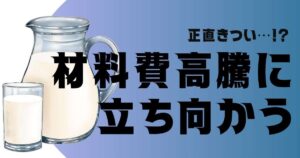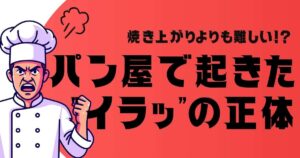バタフライピーがスイーツ界に波を起こす理由 —— 職人が使いこなす“青の魔法”
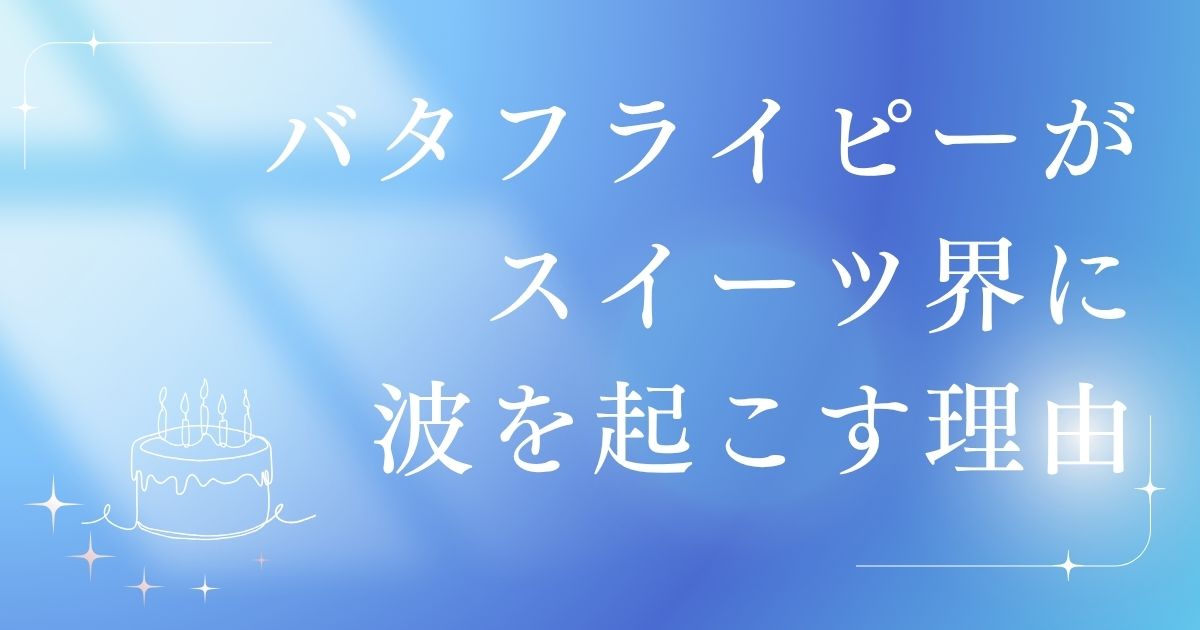
青く透き通るゼリー、生クリームの淡い色味とのコントラスト、スライスフルーツとの重なり合い…。一見、非日常感をまとったスイーツは、「青」という色を透過的な魔法に変える。
その主役として、今スイーツ界で注目度を急上昇させているのが、バタフライピーだ。

もともとは東南アジア原産のハーブティー素材として知られてきたバタフライピー。しかし、その「青」の強さと、酸との相互作用による変色特性──紫やピンクに変わる色変化の演出性──が、SNS映え志向と相性良く、多くのパティシエのアンテナを刺激している。最近では、ソフトクリーム、ムース、クリーム、ゼリーなど多彩なスイーツでその名を目にする機会が増えてきた。
本記事では、バタフライピーの基礎知識から、流行の背景、パティスリーで使うための実践ポイント、応用アイデア、リスク管理まで、職人が即使える「青の魔法」のレシピ集としてまとめる。
青という素材を味方につけることは、見た目の差別化だけでなく、話題性・ブランド性を引き上げる可能性を秘めている。この記事をきっかけに、あなたのお店で「青い一品」を生み出すヒントを持ち帰ってほしい。

なぜいま、バタフライピーが注目されるのか?
いま、全国のパティスリーの現場で「青いスイーツ」が静かに広がりを見せている。
その中心にある素材が、バタフライピー。東南アジア原産のマメ科の花で、ハーブティーやナチュラルカラー素材として知られている。特徴は、抽出液がまるでインクのような鮮やかな青を示すこと。そして、酸との反応で紫やピンクに変化するという性質だ。
近年のスイーツトレンドを俯瞰すると、SNSを意識した“映える要素”が求められる一方で、「人工的すぎる色」は敬遠される傾向にある。その中で、自然由来の青という希少価値が、消費者にも職人にも響いている。
「青」は心理的に“清涼感”“透明感”“特別感”を与える色で、味覚や季節の印象とも結びつきやすい。夏の爽やかさ、透明なゼリーの中に浮かぶ幻想的な青、乳白色クリームとのコントラスト。そこに“物語”を感じる人は多いだろう。
バタフライピーとは何か? その特徴と由来

バタフライピー(Butterfly Pea)は、学名 Clitoria ternatea。原産地はタイやミャンマーなどの熱帯地域で、古くから飲料や染料として利用されてきた。
色の正体はアントシアニン系色素(テルナチン)。ブルーベリーや紫キャベツに含まれるものと同系統だが、バタフライピーの青は群を抜いて鮮烈だ。酸性条件では紫〜ピンク、アルカリ性では青〜群青色に変化するというpH依存の発色変化を持つ。
つまり、レモン汁を少し加えると色が紫に変わる。
この変化は理科実験のようで、SNSでも“化学反応スイーツ”として話題になりやすい。
発色の安定性は光・温度・酸に左右されるが、工夫すれば加熱・冷菓どちらにも使える汎用素材でもある。
ブームのきっかけと広がり

バタフライピーの注目が高まったのは、まず飲料分野だ。透明なグラスに氷を浮かべ、青から紫へ色が変化するドリンクがSNSで瞬く間に広がった。
その流れがスイーツに波及したのは、「自然素材で“映える”色を作りたい」というニーズが背景にある。
冷菓やゼリー、ムース、グラサージュといった透明・半透明のスイーツは、色を魅せるキャンバスとして最適だ。
また、白ベースのクリームやパンナコッタなど“淡色生地”との相性もよい。
最近では、グラスデザート、ケーキの層構造、マカロン、シフォンなど、幅広いカテゴリーで青系の色味が取り入れられつつある。
一方で、このトレンドには「ナチュラルな色で驚きを生む」という新しい価値観も見える。
かつて“色を付ける=人工的”という印象だったが、いまは“自然で鮮やか”がテーマ。
健康志向の高まりや、環境に配慮した素材選択の流れも後押ししている。
パティスリーで使う際の実用性
ここからは、実際の製造現場に立つ職人の視点で、バタフライピーの“扱いやすさ”を見ていこう。

● 抽出と発色
乾燥花をお湯に浸すだけで青色が得られる。
濃度を調整することで、淡い水色〜深い青まで自在にコントロール可能だ。
また、ミルクやクリームに加える場合は、少量のシロップなどを介して均一に混ぜると色ムラを防げる。
● 風味と香り
クセが少なく、ほぼ無味無臭。素材の味を邪魔しないため、フルーツや乳製品との相性が良い。
ただし、あまりに濃く抽出するとわずかに草っぽさが出るため、発色と風味のバランスを探ることがポイントだ。

● 安定性と保存
光や酸に弱く、長時間放置すると退色する。
特に、レモン・ヨーグルト・ベリー系など酸性素材と合わせると紫寄りに変化する。
逆に、クリームやカスタードなど中性〜アルカリ寄りの生地では鮮やかな青を保ちやすい。
● コスト
一般的な天然色素素材と同程度。
乾燥花タイプ、パウダータイプ、液体エキスなど用途に応じた形態がある。
食品添加物として認可されている範囲内で使える点も安心材料だ。
応用アイデア集:職人が遊べる“青の使い方”

バタフライピーを扱う上での魅力は、発色だけでなく変化そのものをデザインにできること。
ここでは、パティスリーで応用しやすいアイデアをいくつか紹介する。
グラスデザートでの層構造演出
下層にヨーグルトムース(酸性)、上層に青ゼリー(中性)を重ねると、淡い紫〜青のグラデーションが自然に生まれる。
青いグラサージュやマーブル仕上げ
白チョコのグラサージュに少量の抽出液を混ぜると、透明感のある水色に。
マーブル状に仕上げれば、海や空を連想させる表情を出せる。
変色演出で“驚き”を作る
食べる直前にレモンソースをかけると、紫に変化する。
動画・SNS投稿との親和性が高く、販促効果も期待できる。
ナチュラルブルーのクリームや生地
ホイップクリームやメレンゲを淡く染めると、ケーキデコレーションが上品に。
人工色素では出せない柔らかいトーンが特徴だ。
焼き菓子やパン系への応用
加熱すると青はやや退色するが、マーブル状に仕込むことでニュアンスを残せる。
バタフライピー入りシロップを使用するなど、焼成後に色を補う工夫も有効。
リスクと注意点

天然素材である以上、使いこなしにはいくつかの落とし穴もある。
特に留意すべきは以下の3点だ。
pHによる色変化の制御
pHが変わると色が安定しない。ベース素材との相性確認が必要。
試作時は必ず少量でテストし、完成後も冷蔵条件での退色を確認したい。
光劣化と保存
透明カップ商品やショーケース展示では、紫外線で色が抜けやすい。
UVカットフィルムやカバーを併用し、販売時間内での劣化を防ぐ工夫を。
消費者理解と安全性
天然とはいえ、アレルギーや体質による反応には注意。
成分表示を明確にし、“天然色素である”ことを伝えることで安心感を与えられる。
職人にとっての“次の一手”

この素材の真価は、「色で遊ぶ」だけにとどまらない。
バタフライピーをきっかけに、素材の色・科学・ストーリーを掛け合わせた商品開発を考えることができる。
小ロットでの試作を繰り返し、色の変化を味方につける。
限定商品としてSNSで話題を作る。
“自然素材×テクノロジー”をテーマにした新ブランド展開を構想する。
消費者は今、“本物らしさ”と“新しさ”の両方を求めている。
「味」「見た目」「素材のストーリー」を同時に訴求できる素材は、そう多くない。
バタフライピーは、その数少ない候補のひとつだ。
青の可能性を味方に
スイーツづくりは、味だけでなく「記憶を残すデザイン」でもある。
バタフライピーの青は、驚きと安らぎ、自然と科学の境界を曖昧にする。
そこに“職人の感性”が加わったとき、単なる流行素材ではなく、
新しいスイーツ文化を形づくるきっかけになるはずだ。
青という色は、難しい。けれど、それゆえに美しい。
あなたの手の中で、どんな青が生まれるか──。
次の一手は、すでにあなたの厨房にある。