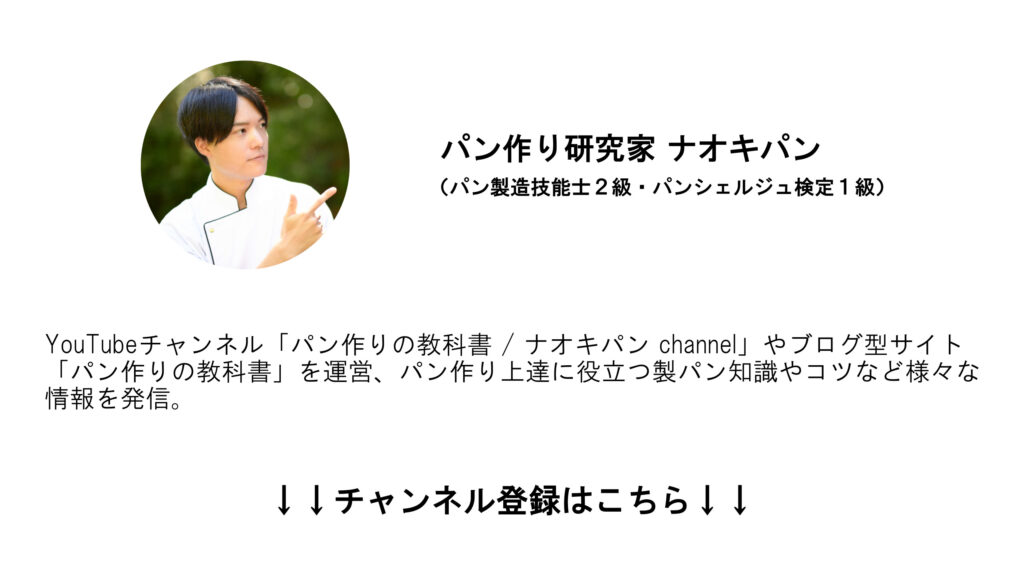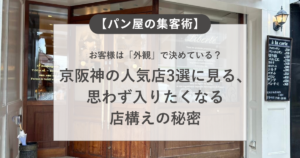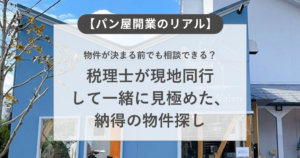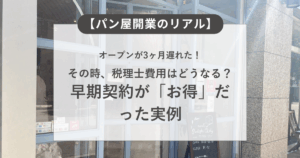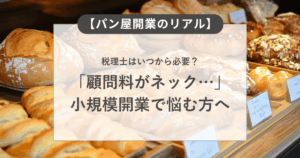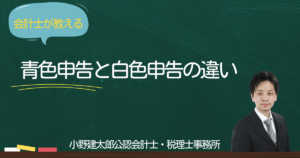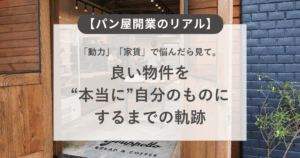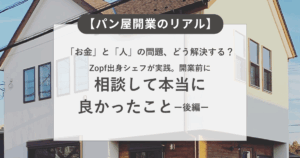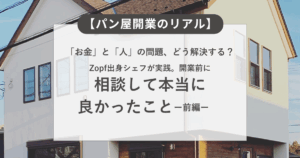歯切れ・口溶けの良いパンを作る方法

日本で流通しているパンの多くは、グルテン量の多い北米産小麦を主体としたものです。
機械耐性や作業性が良く膨らみも大きいといったメリットがある一方で、
・引きが強い=歯切れが悪い
・口溶けが悪い
といったデメリットも存在します。
そんな中で、個人パン店では歯切れ良く口溶けの良いパンを作ることで大手パンメーカーとのわかりやすい差別化を図る動きも見られます。
味の違いは人によって感度に個人差があり「わかる人にはわかる」程度に収まりがちですが、食感の違いは舌が肥えてるか否かに関わらず比較的誰にでもわかりやすい変化です。
なので、食感に目を付けて差別化を図ることも視野に入れてみてはいかがでしょうか?
ここでは歯切れ・口溶けの良いパンを作るための方法をご紹介します。
グルテン量を減らす

グルテンの多い粉で作った生地には強い弾力がありますよね。
基本的に生地の質感はそのまま焼きあがったパンの食感にも引き継がれるため、生地のグルテン構造が強いほどパンの歯切れも悪くなると考えて良いでしょう。
また、口溶けというのは咀嚼中にどれだけ食物が唾液に溶けやすいかによって決まります。
唾液に含まれている酵素はでんぷん分解酵素なので、でんぷん分解は得意ですがたんぱく質分解は苦手です。
「グルテン量が少ない=でんぷん割合が多い」とも言えますので、それだけ口溶けも良くなります。
☆たまごボーロとパンの口溶けを比較してみて下さい。たまごボーロが一瞬にして溶けてしまうのは成分のほとんどがでんぷんだからです。
粉の成分表示に「たんぱく質:〇g」と記載されているはずなのでその数値を目安にするのが最も簡単ですが、この数値にはグルテン以外のたんぱく質も含まれるので、数値が同じでもグルテン量が同じとは限りません。
また、グルテンの質も粉によって異なるため、モノによっては数値が低いのに強い生地が出来る場合もあります。
そのあたりは実際に作ってみて判断するしかありません。
ビタミンC不使用のイーストに変える

意外とみなさん見落としがちなところが、イーストの種類です。
インスタントドライイーストには酸化剤「ビタミンC」が添加されており、生地のグルテン酸化を急激に促進することで作業性・グルテン強度・ボリュームなどを改善する効果があります。
しかし、強力な酸化効果をもたらすため焼きあがったパンの歯切れも悪くなる傾向にあります。
試しにセミドライイーストや生イーストに変えてみて下さい。
生地感や食感の違いに驚かれるはずです。
油脂を増やす

油脂を増やすことによってもパンの歯切れ良さは向上します。
試しに基本の食パンを油脂無しで作ってみたところ、明らかに引きが強くむっちりとした食感に変わってしまいました。
そういう食感が好きな人には好まれそうですが、たった5%の油脂が有るか無いかだけでも歯切れの良さが大きく変わるということです。
油脂の種類を変える

油脂の量だけでなく、種類にも着目してみてください。
どんな種類でも油脂を増やせば歯切れの良さは向上します。
しかし口溶けはかえって悪く感じられる場合もあります。
口溶けの良し悪しに関わってくるのは、使用した油脂の融点です。
口の中でいかに早く溶けるか、それが重要です。
ショートニングやマーガリンなどは工業的に作られているため、どのメーカーも様々なタイプを取り揃えており、融点も様々です。
融点が高い油脂は多量に使用してもホイロ温度を下げる必要が無いなどメリットもありますが、その分口溶けは悪くなるでしょう。
口溶けに焦点を当てて作る際は、油脂の規格書を確認してみると良いかもしれません。
卵白を使用しない

パン作りで卵を使用する際、全卵として使用するケースが多く見られます。
しかし、ブリオッシュのように油脂を大量に使うケースでなければ、卵白をカットして卵黄のみで使うことをオススメします。
卵白を使用するとミキシングに時間がかかるだけでなく生地のベタつきも増え、そのくせ卵白のたんぱく質成分が焼きあがったパンの第二の骨格として機能してしまうため歯応えが強くなってしまうのです。
卵の比率は「卵黄:卵白=1:2」です。
全卵6%のレシピなら卵黄2%に変更し、カットした卵白4%分の水分を仕込み水として増やすだけ。
全卵8%配合のホテルブレッドで比較実験したところ、十分にわかる程度には歯応えに差が生じました。
ただしブリオッシュのように大量の油脂を使う生地で全卵から卵白の全てをカットしてしまうと、非常に脂っこくモッタリとした食感になってしまう印象があるので、一部カットする程度に抑えた方が良さそうです。
ケースバイケースで対応してください。
捏ね具合を控えめにする
あえてこね具合を控えめに作る製法も近年流行っていますが、ミキシングによるグルテン酸化促進が最小限で抑えられることで歯切れの良さに繋がります。
また、素材の風味がよりダイレクトに活きるというメリットもあります。
しかしそれがかえってデメリットとなる場合もあり、例えばイーストを多く使うパンではイースト臭がダイレクトに活きてしまい美味しくないパンが出来上がってしまいます。
また、材料のチョイスや工程のチョイス次第でクオリティに大きな差が出るため、本当に美味しく作るには知識とコツが必要です。
高加水にする
高加水製法もパンの歯切れ・口溶けを良くする手段と言えます。
そもそもパンの口溶けというのは、咀嚼していかに早く唾液に溶け込むかで決まります。
スコーンを食べると口の中の水分が全部持っていかれる、なんて経験ありませんか?
どんなにグルテン量が少ない生地でも、水分量が少ないと口溶けに必要な唾液が不足してしまうのです。
日本人は元々唾液量が少なく、かつ年齢が上がるにつれて減少する傾向にあります。
だから今日まで長いこと主食の座に米が鎮座していたわけです。
歯切れに関しても同様で、例え全く同じ種類の粉を使って水分量以外は同じ配合の場合でも、比べると高加水の方が歯切れは良くなります。
火通りを改善する
火通りの良し悪しというのは、「生焼けか否か」という極端なものだけではありません。
一見しっかり焼けているようでも、焼成時間が極端に短かったり発酵具合が不適正であったりすると、熱通りが悪くなることからでんぷんの糊化度が低い状態で焼きあがってしまいます。
火通りを改善する方法は、とにかく基本をしっかり見直すこと。
捏ね具合から発酵具合の見極め、焼き時間や焼き色まで全てが火通りに関わってきます。
製法に色々なアレンジを加えるのも良いですが、まずは基準となる基本をしっかり身に付け、正解の食感や味を覚えておくことをオススメします。
この記事を書いた人