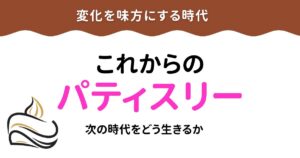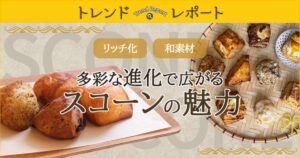「これからのパティスリー」—次の時代をどう生きるか
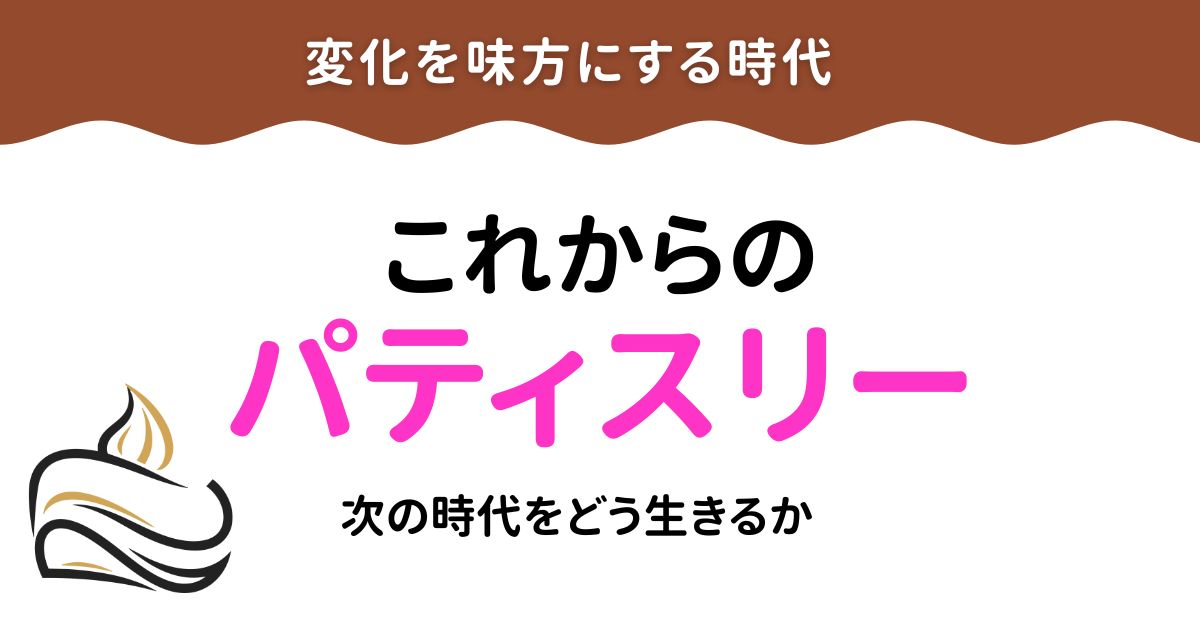
パティスリー業界の今

今回はパティスリー業界の現状とこれからについて考えてみたいと思います。
かつては街のいたるところにあった洋菓子店。だが近年、その数は確実に減り続けています。
総務省のデータによると、全国の菓子製造小売業(和菓子を含む)は2007年の約3万店舗から、2022年には約2万3千店へと3/4の規模にまで減少。
2024年度の洋菓子店倒産件数は過去最多の51件にのぼっています。
これには周りを取り巻く環境や物価高の影響などにうまく対応できていない等、様々な現状が考えられます。
なぜ、いま苦しいのか

これはパティスリー業界に限ったことではないですが、
まず直面しているのは原材料費の高騰があります。
バターは前年より8~15%ほどの値上がりし、カカオ豆は2024年春に史上最高値を記録。小麦、砂糖、卵なども軒並み上昇しており、値上げに踏み切れない個人店の経営を圧迫しています。
次に深刻なのが人手不足と離職率の高さ。
パティシエの世界では「3年で9割が辞める」とも言われているほどで、長時間労働と低賃金、職場の人間関係などが理由に挙がります。人が定着しないことで製造量の安定や品質維持が難しくなり、結果としてお客様との信頼も損なわれやすい傾向が強いです。
そしてもう一つの壁が、コンビニスイーツとの競合。価格は抑えつつクオリティは年々上がり、SNS映えも意識した商品が続々登場。
“ちょっとしたご褒美”の需要を、かつて街のケーキ屋が担っていた層がコンビニへ流れました。同じ「おいしいスイーツ」でも、どこで買うか・誰から買うかの時代に入ったといえるでしょう。
変わるお客様の価値観

消費者の意識も大きく変化しています。
「節約と贅沢を使い分ける」という“メリハリ消費”が定着し、
・日常にはコスパ重視のスイーツ
・特別な日には高級パティスリーのケーキ
という二極化が進んでいる。
つまり、“全部高い”“全部安い”ではなく、「自分にとって価値のある選択」が基準になってきているのでしょう。
お客様が“価値”で選ぶなら、職人の想いや体験を届けるパティスリーには、まだ多くの可能性が残されているともいえます。
再定義の時代へ:パティスリーの生き方改革

これからの洋菓子店に求められるのは、「作る」だけでなく“伝える”力 だ。
味の良さはもちろん、素材へのこだわり、背景のストーリー、シェフの想いをどれだけ魅力的に伝えられるかが重要になると考えられます。
それがお店のブランド化に繋がっていきます。
SNSやEC、冷凍配送、ポップアップ出店など、多様な販売ルートを持つことも、もはや特別ではなく。“製造小売”から“ブランド発信者”へと変わるタイミングに来ているのではないでしょうか。
また、現場では働き方の見直しも欠かせません。
冷凍や副材料を活用した効率化、製造チームの分業化、営業時間の短縮など、「持続可能な職場づくり」は若手定着のカギとなります。
最近は、時代の流れもあり、技術を守りながらも“働きやすい現場”を目指す店が少しずつ増えています。そのようなお店の取り組みや考え方をこちらでも積極的に発信していけたらと考えています。
2025年のトレンド感
2025年のトレンドを見ると、フランやカヌレなどフランス伝統菓子の再評価が進む一方で、グリークヨーグルトや植物性素材など健康志向のスイーツも伸びています。
また、ピスタチオや米粉といった素材そのものの魅力を打ち出す店も増え、
「甘いものを食べることへの肯定感」を取り戻す流れが起きている。
そこには、“体にいい”と“心にいい”の両立を模索する時代のニーズがあるように感じます。
パン業界とも重なる構造的課題
実はこの流れ、パン業界とも非常に似ています。
原材料高騰、人材不足、そしてチェーン・コンビニとの競争。
「個人店がどう個性で勝つか」という課題は、ベーカリーもパティスリーも共通の課題として取り上げられることが多いです。
お客様が“人”や“物語”に惹かれるのも同じ。
作り手の顔が見えること、地域とつながることが、作るだけでなく伝えていく。という動きがこれからの小さな店の強みになっていくと考えられます。
技術の時代から、共感の時代へ

お菓子は嗜好品であり、同時に「誰かを思う気持ちの象徴」でもあると思います。パティスリーの価値は、味や技術だけでなく、そこに込められた想いが共感されるかというのも大事な要素です。
時代が変わっても、「誰かを笑顔にする」お菓子づくりは変わらない。
変えるべきは、その伝え方と働き方。
——パティスリーという仕事を“再定義”する時が来ているのではないでしょうか。