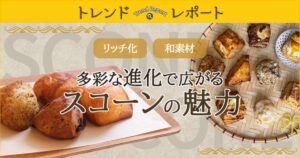5分でわかる蒸しパン ~歴史・起源・雑学~

蒸しパンの歴史と魅力を探る

ふわふわでほっとする味わいの「蒸しパン」。
家庭のおやつのイメージが強いですが、そのルーツをたどると日本の和菓子文化、中国の饅頭、近代製パン技術の交差点が見えてきます。
本記事では、蒸しパンの起源と歴史、そしてシェフたちにも新たな発見があるような雑学を紹介します!
蒸しパンの起源と歴史

日本の蒸しパンのルーツは諸説ありますが、一説には中国から伝わった「饅頭(まんとう)」が大きく関わっています。
饅頭はもともと肉や餡を包む惣菜系と、具材を入れない“白饅頭”のような素朴な蒸しパン系がありました。
江戸時代、和菓子文化と交わり「酒饅頭」など、酒粕の酵母を使った発酵生地が普及し、蒸して作る方法が庶民に広まりました。
明治以降になると洋風パンの製法が入ってきて、重曹やベーキングパウダーで簡単に膨らませる“蒸しパン”が一般家庭でも作られるようになります。
蒸しパンの製法と特徴

蒸しパンの特徴は、焼かないことで水分が保たれ、しっとりふわふわな食感になることです。バターや油脂が少なくても満足感があり、小麦粉の代わりに米粉を使うことでグルテンフリー商品としても注目されています。
最近では韓国の“インジョルミ蒸しパン”のように、和素材やアジアンテイストを取り入れた蒸しパンも人気。
焼き菓子との差別化として、“蒸し”だからこそできる季節素材の香りを活かしたり、低脂質・ヘルシー志向で提案する店も増えています。
また、焼き設備を使わずに小ロットで作れる点も、小さなベーカリーにとっては大きな魅力。
ちょっとしたラインナップの一角に加えるだけで、蒸気の香りが店内に漂い、違う雰囲気を演出できます。
失敗しない蒸しパンの「穴あき現象」

蒸しパン作りでよくあるのが、“表面に穴が開く現象”。
これは蒸気が一気に生地に当たって爆発してしまうためです。
昔の職人さんは「釜の蓋にふきんをかける」「布で蒸気をやわらげる」など、家庭でもできる一工夫を編み出していました。
ちなみに面白いのは、昔の蒸しパン屋台では蒸し器のフタを開けると湯気が立ち上り、その香りが通りすがりのお客さんを引き寄せる“香り営業”になっていたとか。
今でも屋外イベントやマルシェで蒸しパンを提供する時に「湯気の演出」は販促のひとつとして有効かもしれません。
サクッとまとめ!
蒸しパンは、饅頭文化を源流に、
家庭で親しまれながらもパン屋に新しい可能性を残す“焼かないパン”です。
低油脂で軽く、香りのバリエーションを活かせる点は、ヘルシー志向やアジアンフレーバーの提案にぴったり。
この記事を通じて、パン業界の皆様に蒸しパンの魅力を再発見し、新たなインスピレーションを得ていただければ幸いです!