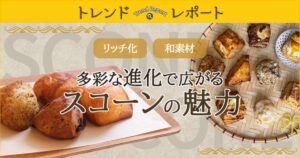5分でわかるサワードウ ~歴史・起源・雑学~

サワードウの歴史と魅力を探る

いま改めて注目されている“サワードウ”。
天然酵母による複雑な発酵と独特の酸味、そして手間のかかる製法は、効率化が進む時代に逆行するようでいて、むしろ職人の心を揺さぶる魅力に満ちています。
本記事では、サワードウの起源と歴史、そしてシェフたちにも新たな発見があるような雑学を紹介します!
サワードウの起源と歴史

サワードウのルーツは、紀元前3000年頃の古代エジプトまでさかのぼります。
最初のパンは、空気中の天然酵母によって偶然発酵してしまった粥状の小麦だったと考えられています。
この“偶然”を受け入れ、発酵という技術に昇華させたことが、人類の食文化における大きな進化のひとつになりました。
冷蔵庫もドライイーストもなかった時代、人々はスターター(サワー種)を受け継ぎ、手の感覚と経験で日々の発酵を調整していました。
サワードウの製法と特徴

サワードウの最大の特徴は、なんといっても「生きた酵母と乳酸菌の共同作業」による発酵です。
スターター(サワー種)は、時間とともに微生物のバランスが変化し、環境によって性質も風味も大きく左右されます。
パン生地に加えるタイミング、スターターの水分量や熟成具合、室温や発酵時間。
ひとつひとつが味や食感に直結するため、レシピ通りにはいかないのがサワードウ。
だからこそ、職人の経験と勘、そして観察力が問われます。
また、人工的なイーストによる発酵とは異なり、発酵スピードは遅めで、作業にも時間がかかります。
しかしその分、グルテンの分解が進みやすく、消化の良さや保存性の高さも魅力のひとつです。
酸味のある風味が苦手な方には難しい面もありますが、その分、粉の持つ香りや個性が際立ちます。
サワードウは、いわば「育てて作るパン」。
焼く直前まで変化し続けるパン生地と向き合うことで、パン作りの原点を思い出させてくれる存在です。
サワードウ~スターターは家族同然!?~

サワードウのスターター(サワー種)は、パン職人にとって“酵母の塊”というよりも、もはや「相棒」のような存在。
実際、スターターに名前をつけて育てている職人は世界中に数多くいらっしゃいます。
「レオ」「サム」「はっこうくん」など、名前も個性的で、愛着の深さが伝わってきます。
また、スターターの「世代交代」にも文化があります。
とあるベーカリーでは、初代スターターの「孫」にあたるスターターを使い続けており、店の壁には「家系図」まで貼ってあるとか!
さらには、スターターに遺言を残し、跡継ぎの職人に託して他界されたという話もあり、その存在感はまさに家族同然です。
スターターは酵母と乳酸菌の集合体でありながら、パンに命を吹き込んでいるのです。
サクッとまとめ!
サワードウは、時間も手間も気力もかかります。
ですが、毎日変化するスターター(サワー種)と向き合うことで、職人の五感は鋭くなり、パンへの愛情も深まっていくと感じます。
この記事を通じて、パン業界の皆様にサワードウの魅力を再発見し、新たなインスピレーションを得ていただければ幸いです!